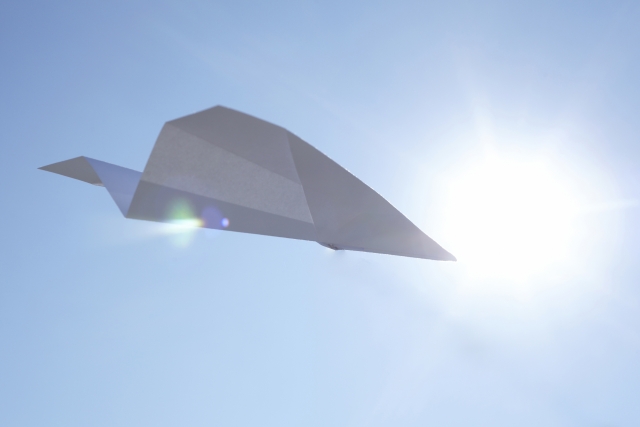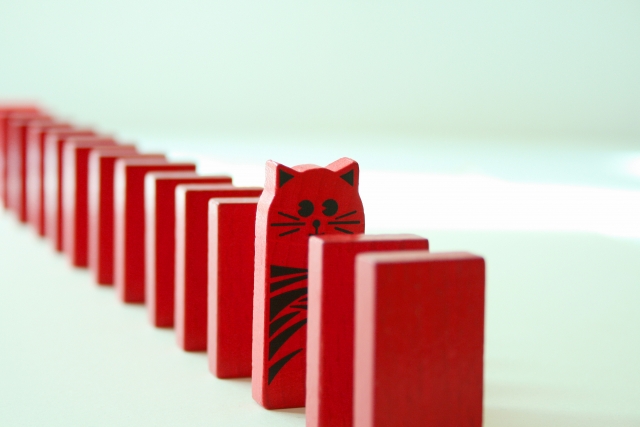あと3時間で研修に出発!・・・という時に
偶然出会ったある方が、「ねえ、聞いてよ」と話しかけてきました。
「もうムリ~今日は本当にいろんなことがあって・・・散々だった~。」
ネガティブな感情と共にすごく話を聴いてほしそうなのがわかりました。
「さあ、私、どうする?」
瞬間的にこの問いが立ち上がり、私の中のコンピューターが作動
研修時間にギリギリだったらまだ簡単な選択だったのかも?
3時間という時間がある意味微妙だったからこそ迷いました。
困っている人を助けたい
人に親切にしたい
相手を大切にしてちゃんと人の話を聴きたい
そこには純粋な想いと、「ねばならない」という価値観が同時にある
しかし、研修先の受講生の方の立場に立つと
ここで話を聴くことは準備時間のロスになる
ネガティブな感情を引き受けることで研修までに自分を立て直せるのか?
エネルギーを高く保つ、とっておく必要があるのです。
話を聴くことは、受講生の方を大切にできないことになる
その時私がとった行動は・・・
「ごめんなさい、今研修前で話を聴くことができない」
お断りをする方の選択でした。
その代わり、研修後たっぷりじっくり話を聞こう!!
そして、研修が終わってから会いました。
私の選択が本当に正しかったかどうかわかりませんが、
私がかけつけたことに対して、驚いてとても喜んでくださいました。
あの時の強いネガティブな感情も時間の経過とともに薄れて冷静になっていて
「たいしたことじゃなかった」と・・・
本当にケロリと言うので2人で大笑いしました。
相談された時にすぐに話が聞けない時がある
時間を気にして傾聴はできない
「後にして!」と遮断しても後悔が残るでしょう。
この出来事を振り返った時に、
もう少しこのように伝えればより良かったな~と振り返る自分がいる
もう少し(さらに)相手を大切にした私だったら?と思う自分がいる
「今は・・・(理由)で話を聴けないけど、終わったらじっくり聴くよ」
相手を大切にしてメッセージを伝えることが今よりさらにできたら
今以上に安心感を提供してさしあげることが出来ると思いました。
あまりにも、相手の方の雰囲気がガラリと変わっていたので???
まるで私がどう対応するかの進級テストを先生から出されたかのよう(笑)
自分への振り返りをまた次に活かしていこうと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。