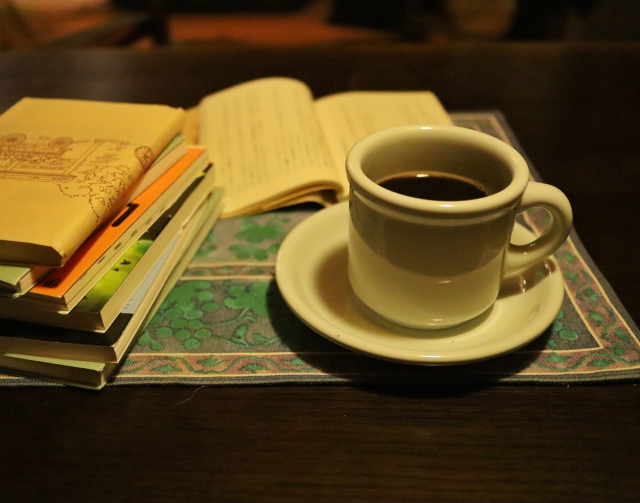もし、相手が不満を言ってくることに悪いイメージしかもっていなかったら?
とっさに(無意識的な反応として)身構え緊張感を高めるでしょう。
嫌悪感や恐怖を感じるかもしれません。
相手から身を守るために、こちら側の正当性を主張したくなるかもしれません。
すると、相手はさらに緊張感を高めて身構えます。
それでは、もし・・・
相手が不満を言ってくることへのメリットの視点も持っていたら?
面倒くさいな、嫌だなと思う部分も確かにあるけれど
そう感じてしまう自分自身の存在もちゃんと認めることができていて
その上で、確かに一理あるかもしれないと相手の視点にも立ってみれる
そう感じる人は他にもいるかもしれないとも思ってみれる
正直に打ち明けてくれたことに対して感謝の気持ちをもつ
ありがたいフィードバックだと思う
或いは現場を変えるチャンスだと思う
「誰かから不満を言われる」ことに対しての視野が広い状態
すると、随分と気持ち穏やかにニュートラルに言葉を返すことができる
「〇〇さんはそんなふうに感じているのですね。」
このニュートラルなエネルギーをまとったあなたからの言葉で
相手は、ちゃんと「伝わった感」「受け止めてもらえた感」を感じます。
「受け止める」は、「受け入れる」や「賛成する」こととは違います。
「〇〇さんはどうしたら良いと思う?」
不満を提案に変えさせる質問につなげたり
現場や自分を振り返ったとしたら、本当に不満をチャンスに変換できますね。
最後までお読みいただきありがとうございます。